自身のルーツであるサイケデリック・フォーク(サイケデリック・フォーク・バンド、Spires That in the Sunset Riseのメンバーとしても活動してきた)の枠を遥かに超え 、実験的なサウンドと橋渡し、生々しく境界を押し広げる、ヴォーカリスト/マルチ・インストゥルメンタリスト/コンポーザーのKa BairdがRVNG Intl.か3/22にリリースする新作アルバム『Bearings: Soundtracks for the Bardos』からセカンド・シングルとなる「Gate IX」がリリースされ、ミュージック・ビデオも公開されました。
Ka Baird new single “Gate IX” out now
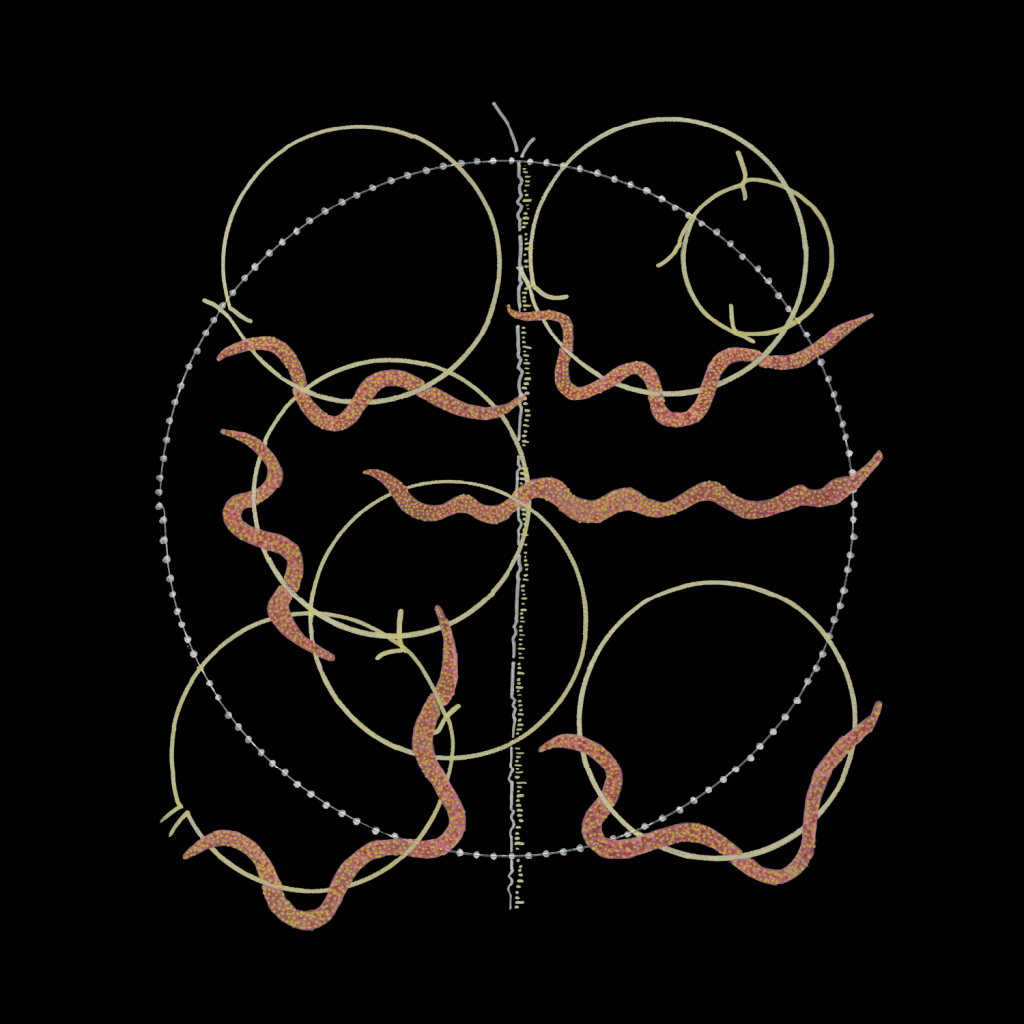
Artist: Ka Baird
Title: Gate IX
Label: PLANCHA / RVNG Intl.
Format: Digital Single
Listen/Buy: https://orcd.co/pvm74pn
Ka Baird – Gate IX [Official Video]
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jQJSRdL9pXs
Shot and directed by Sebastian Mlynarski. Edited by Ka Baird.
Ka Baird new album “Bearings: Soundtracks for the Bardos” out on March 22

Artist: Ka Baird
Title: Bearings: Soundtracks for the Bardos
Label: PLANCHA / RVNG Intl.
Cat#: ARTPL-209
Format: CD / Digital
※解説・歌詞対訳付き予定
Release Date: 2024.03.22
Price(CD): 2,200 yen + tax
『Bearings』は、芸術の演劇性と精神性が無常を清算し、生と死のサイクルを受け入れる流れの出会いである。
Ka Bairdがソロ・ニュー・アルバム『Bearings: Soundtracks for the Bardos』を携えて帰ってきた。このアルバムは、ニューヨークを拠点に活動するヴォーカリスト、マルチ・インストゥルメンタリスト、コンポーザーの恍惚としたライヴ・パフォーマンスの要素を、ミニマルで臓腑に響くコンポジションに絡めたもので、参加している様々な才人達とのコラボレーションによってその範囲とサウンドを広げている。このアルバムの11の楽章は、独自の多重性によって定義された変幻自在の呼び声として現れ、厳格なコンセプチュアリズムと音楽的技巧に翻弄された状況と悲しみの感情的な結末である。
20年以上にわたり、Kaはパフォーマンスを通してサウンドの外側の次元を探求してきた。そのルーツである1980年代初頭のサイケデリック・フォーク・ムーヴメントを遥かに超え、実験的なサウンド、パフォーマンス・アート、儀式を橋渡しする、生々しく境界を押し広げるソロ・パフォーマンスで知られている。また、ライヴ・セットでは、拡張ヴォイスやマイク・テクニック、エレクトロニクス、フルート、ピアノなどが含まれる。本作は、2017年のデビュー作『Sapropelic Pycnic』、そして高い評価を得た2019年のアルバム『Respires』に続く作品だ。
当初、2022年春にシカゴのLampoから依頼された20分間の作曲とプレゼンテーションとして構想された本作。Kaは、まず、マジシャン、シャーマン、ピエロ、アスリートの間で装いを変える一連の親密なパフォーマンスと、遊びと闘いの両方を伴い、継続的な無根拠の状態に耐える身体的に厳しいパフォーマンスを通じて「Bearings」の概念を探求した。この作品は、その後1年間、瀕死の親を介護する重苦しさと相まって、『Bearings』の土台を築き、アルバムの最終的な物語構成は、翌年9月の母親の死後数ヵ月で明らかになった。
Kaはこう説明する:「このアルバムは、2022年の夏に焦点が当てられ始めた。その年の2月に母が末期の診断を受けた後、私はイリノイ州ディケーターで母と暮らしていた。それからの半年間、私は母が眠っている間の静かな時間に、これらのサウンドを組み立て、アレンジし、創り出す作業をしていた。『Bearings』のライヴ・パフォーマンスと、母の介護と、その死を目の当たりにした経験とが合わさって、このレコードが生まれたんだ」。
『Bearings』は、芸術の演劇性と精神性が無常を清算し、生と死のサイクルを受け入れる流れの出会いである。このアルバムは、11のゲート、中陰、または「中間」に分かれており、それぞれが 停止または経験のギャップの状態を音響的に表し、それぞれが遷移、移動、障害、ポータル、降伏、および解放と相関してる。このような現在進行形の変位と不安定な状態、つまり自分の方向性を見失うこと、そしてその流れるような、酔わせるような形の中に崇高な意味を探し求めることを提案している。Kaの言葉を借りれば、「無常は決して休むことがないので、私たちは常に中陰の中にいる」。
ボルチモアのマルチ奏者のAndrew Bernstein(アルト・サックス)やHorse LordsのメンバーでもあるMax Eilbacher(フルート・プロセッシング、エレクトロニクス)、超絶変態ドラマーGreg Fox(パーカッション)等をはじめ、gabby fluke-mogul(ヴァイオリン)、Henry Fraser(コントラバス)、Joanna Mattrey(ヴィオラ)、John McCowen(コントラ・クラリネット)、Camilla Padgitt-Coles(ボウル、ウォーターフォン)、Troy Schafer(ストリングス)、 Chris Williams(トランペット)、Nate Wooley(トランペット)、そして自身の愛猫Nisa(鳴き声)等豪華面々が参加。Kaとその仲間達は、集団的なハミングと鼓動を生み出すために、ミニマリズムの広大な密度を作り出し、突然のスタートとストップ、複雑なハーモニクスとテクスチャー、パーカッシブな華やかさ、そして単一の周期的な叙情的なフレーズによって区切られた、広大なミニマリストの密度を描き出している。
Kaはこのアルバムを、特定のモチーフがさまざまな構成で繰り返されるソング・サイクルへの逸脱した頷きであると考えている。このアルバムの音の辞書では、トランペットの音は誕生や死を意味し、遠くの弦楽器のモチーフは記憶を表す。『Bearings』は、深い抽象性と集中力を持つ持続的な作品であり、その中で音の要素、構造、意味がひとつの統一された形に到達する。これは、今日の音楽界で活躍する最もダイナミックで妥協のないアーティストの一人であるKa Bairdにとって、創造的な高みに到達した作品に他ならない。
なお、このリリースの収益の一部は、国境なき医師団に寄付される。国境なき医師団は、紛争、疫病の流行、自然災害、人災、医療からの排除などの影響を受けている70カ国以上の人々に、独立した公平な医療人道支援を提供しています。
TRACK LIST:
01. Gate I
02. Gate II
03. Gate III
04. Gate IV
05. Gate V
06. Gate VI
07. Gate VII
08. Gate VIII
09. Gate IX
10. Gate X
11. Gate XI




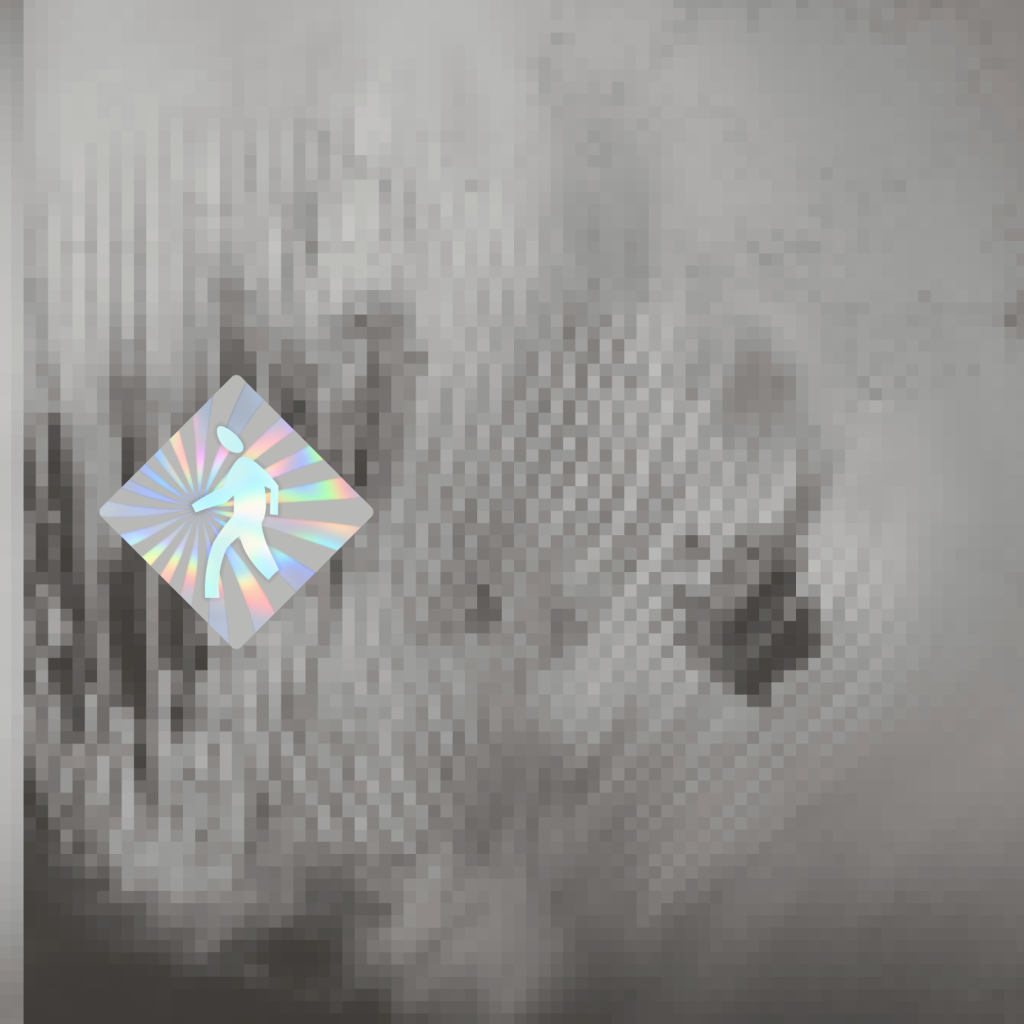

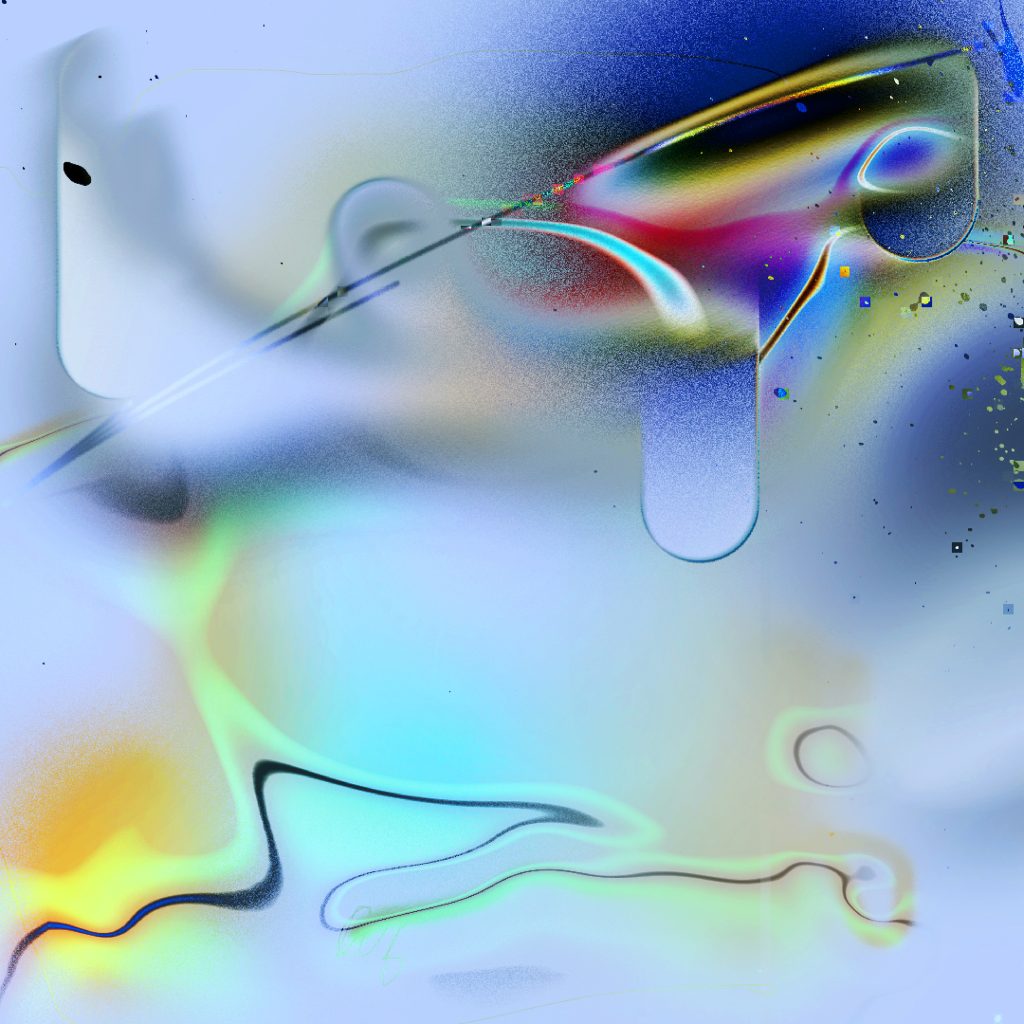
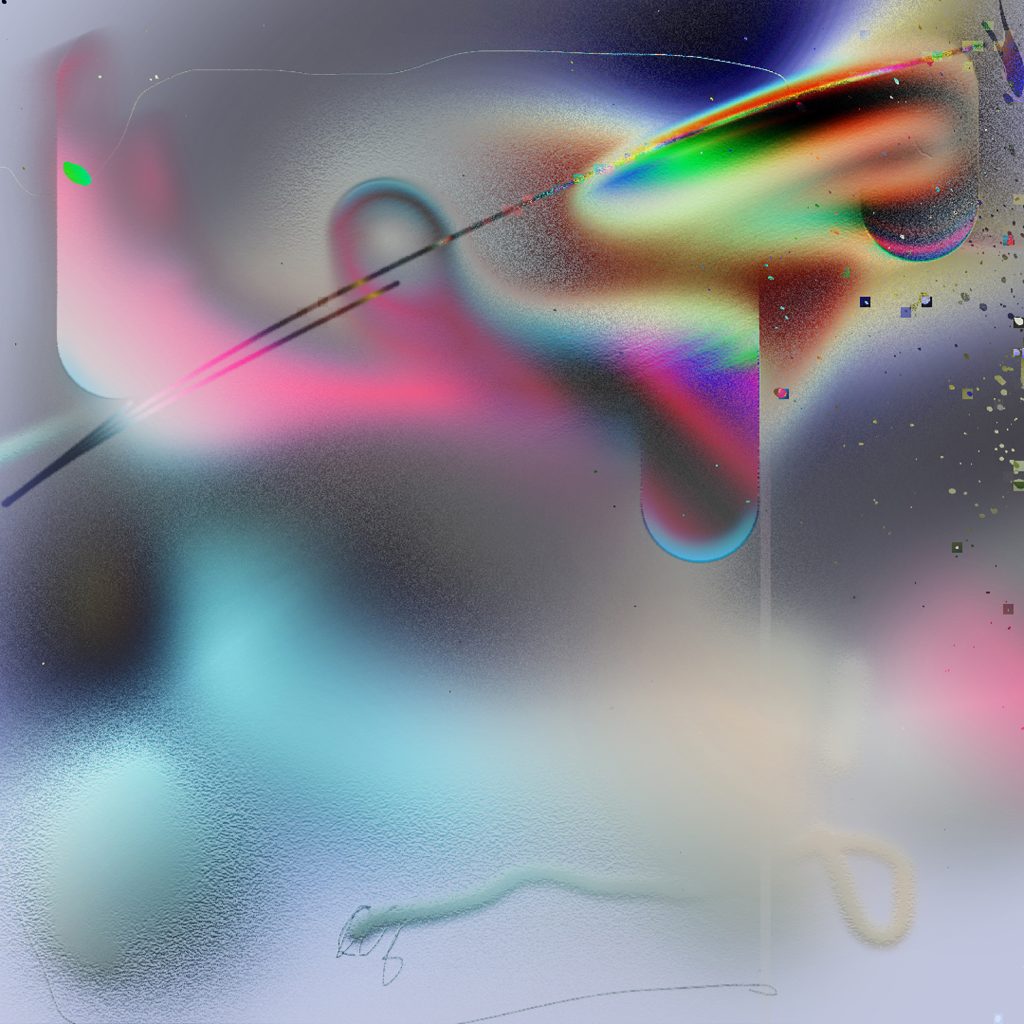

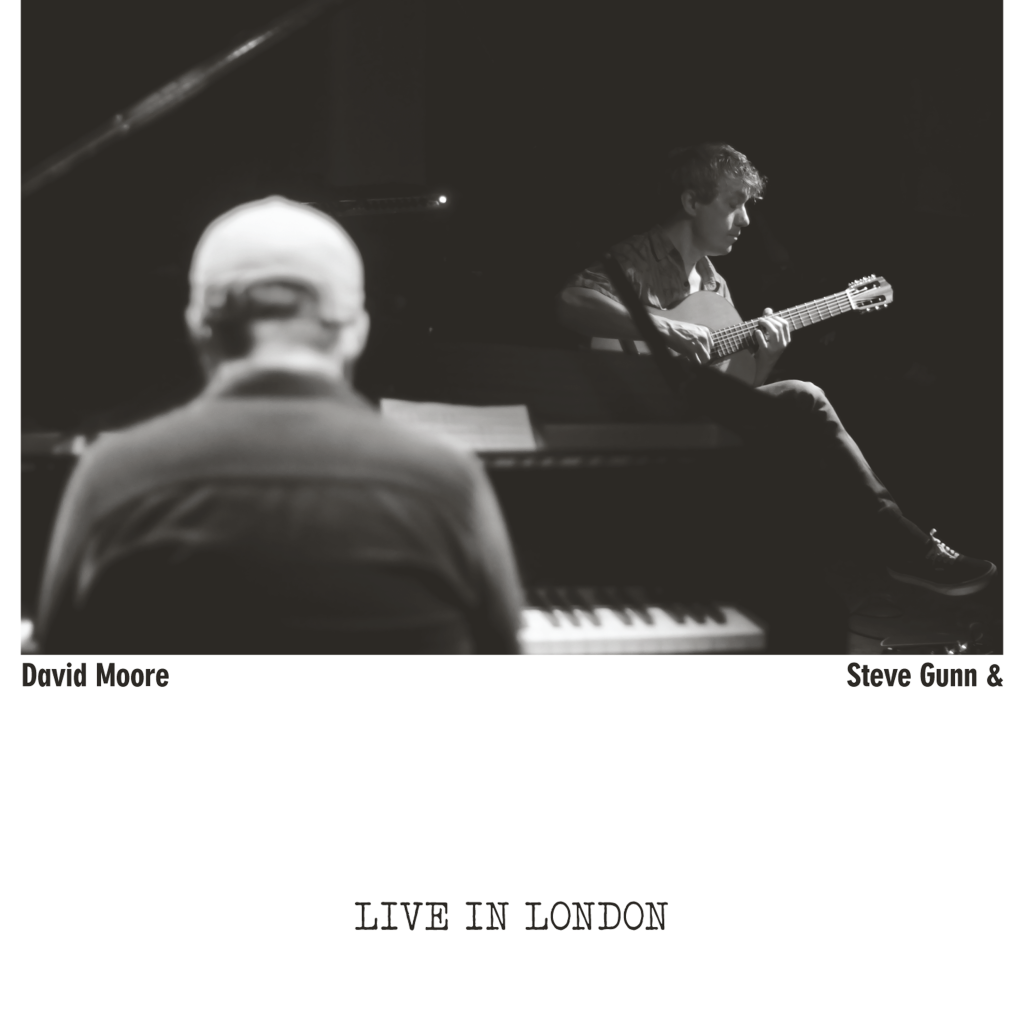


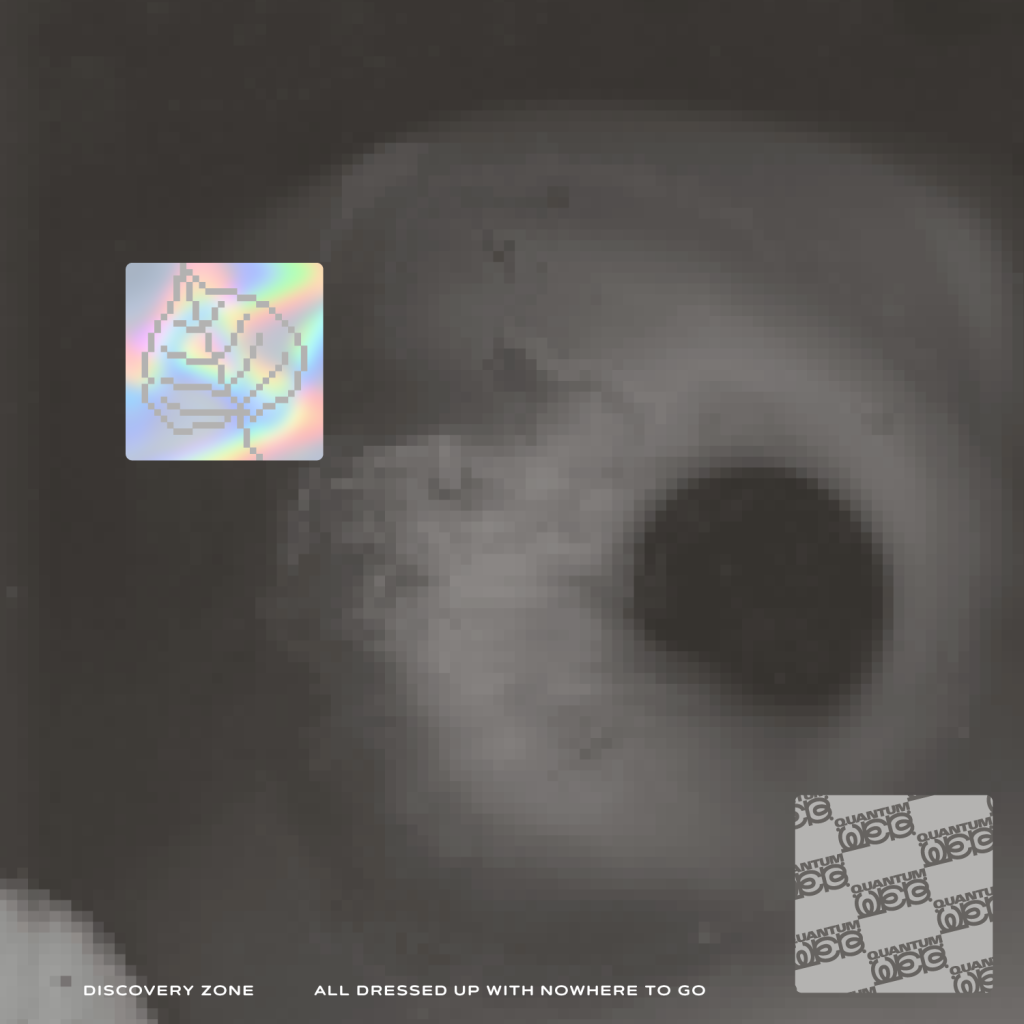





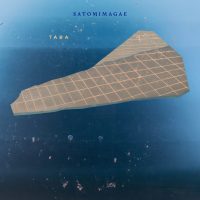




![WHATEVER THE WEATHER “Whatever The Weather II” [ARTPL-230] WHATEVER THE WEATHER “Whatever The Weather II” [ARTPL-230]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2025/01/GI-446_3000x300-200x200.jpg)
![COLIN SELF “respite ∞ levity for the nameless ghost in crisis” [ARTPL-228] COLIN SELF “respite ∞ levity for the nameless ghost in crisis” [ARTPL-228]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2024/11/RVNGNL94_4000px-200x200.jpg)
![RAMZi “moon tan” [ARTPL-227] RAMZi “moon tan” [ARTPL-227]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2024/12/ARTPL-227front-1-1024x1024.jpg)
![TRISTAN ARP “a pool, a portal” [ARTPL-226] TRISTAN ARP “a pool, a portal” [ARTPL-226]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2024/10/WSDMLP008-LP-Cover-Digi-Final-200x200.jpg)
![TIME WHARP “Spiro World” [ARTPL-224] TIME WHARP “Spiro World” [ARTPL-224]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2024/09/SpiroWorld.jpg)